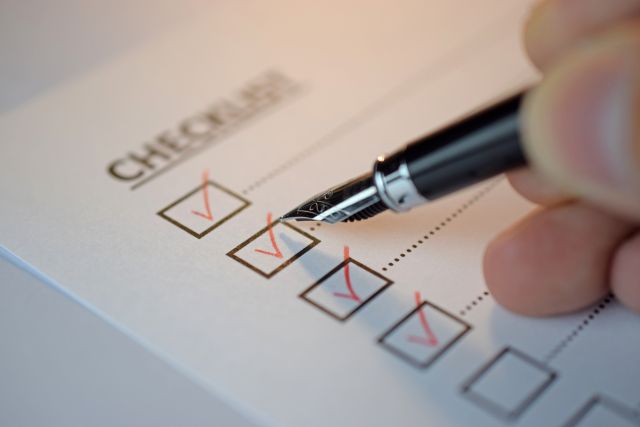BLOG ISOブログ
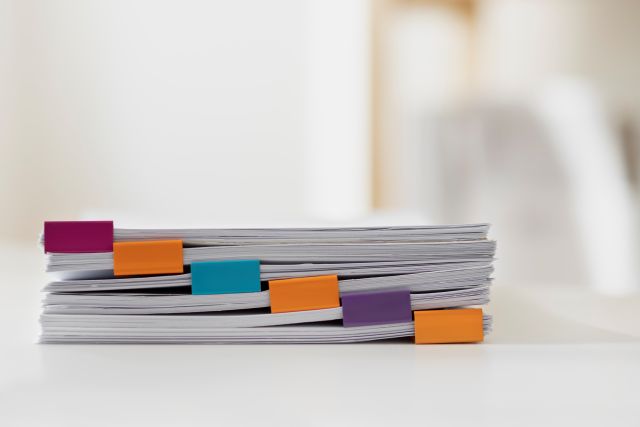
ISO(国際標準化機構)が策定する国際規格は、世界各国の企業および組織に広く導入されており、国際貿易における基準の統一に大きく寄与しています。
中でも「ISO9001(品質マネジメント)」、「ISO14001(環境マネジメント)」、「ISO27001(情報セキュリティマネジメント)は、日本国内でも認知度が高く、多くの企業・組織が導入している代表的なISO規格です。一方で、これら以外にも多数の規格が存在し、それぞれ異なる目的と要求事項により設計されています。
本記事では、企業活動に密接に関わる主要なISO規格の種類とその特徴について解説します。
ISOとは
ISOとは、国際標準化機構のことで、企業・組織の体制構築に関する国際規格を定めている機関です。以下では、ISOとはどのような機関なのか、ISO規格の概要および目的、基本的な仕組みについて解説します。
ISO(国際標準化機構)の概要
ISO(国際標準化機構)とは、スイス・ジュネーブに本部を置く非政府組織で、製品・サービス、マネジメントシステムなどに関する国際的な標準(規格)を策定する機関です。正式名称は「International Organization for Standardization」で、各国の標準化団体が加盟しており、160を超える国・機関が加盟しています。
ISOは、国境を越えた製品・サービスの品質向上および取引の円滑化、安全性の確保、環境保護などの促進を目的としています。代表的な規格は、品質マネジメントのISO9001、情報セキュリティマネジメントのISO27001、環境マネジメントのISO14001などです。ISO認証の取得は、企業・組織における国際的な信頼性・競争力向上に寄与します。
ISO規格の概要・目的
ISO規格とは、製品・サービス、マネジメントシステムにおいて、国際的に共通基準として定められた枠組みです。国際規格として定められており、ISO認証の取得は、国・業界を問わず品質・安全性、信頼性が保証されるため、取引の円滑化および顧客信頼感の向上につながります。
ISO規格は、国際間の技術的障害を取り除き、持続可能な発展・社会的信頼向上に与する体制の構築を目的とする取り組みです。とくにマネジメントシステム規格(例:ISO9001、ISO14001、ISO27001)は、企業・組織が効率的に運営を行い、マネジメント体制の継続的な改善を実現する枠組みとして活用されています。ISO規格は任意基準であるものの、認証取得により外部からの信頼性向上・入札要件への適合、競争力の強化など、幅広い実務上のメリットも見込まれます。
ISO認証取得の基本的な仕組み
ISO認証取得の基本的な仕組みは、企業・組織がISO規格に基づくマネジメントシステムを構築・運用し、規格との適合性を第三者機関(審査機関)が審査・認証する流れで成り立っています。ISO認証の取得にあたり、企業・組織は対象となるISO規格に沿って、必要文書・体制の整備、業務プロセスの見直しを行い、内部監査・マネジメントレビューを実施します。
その後、審査機関による認証審査(初回審査)を通じて、文書・実地審査(現地審査)を受け、要求事項に適合していると評価されれば認証が付与される仕組みです。ISO認証取得後も、最低年1回の維持審査(サーベイランス審査)と3年ごとの更新審査(再認証審査)が実施されるため、継続的な運用と改善が求められます。
ISO規格の「工業規格」「マネジメントシステム規格」とは
ISO規格は大きく「工業規格」と「マネジメントシステム規格」の2種類に分けられます。
以下では、ISO規格の「工業規格」「マネジメントシステム規格」それぞれの特徴・違いについて解説します。
工業規格
ISOにおける工業規格とは、製品の設計・製造・品質管理などにおいて、一定の基準および仕様を定めた技術的な基準です。形状・寸法、性能・材質、試験方法、記号・表示方法などを標準化し、製品同士の互換性および安全性、品質の均一化を図る目的があります。
たとえば、「ねじの規格」「紙のサイズ(A4など)」「電気製品の安全基準」などが、代表的な工業規格です。ISOではこれらを製品規格・技術仕様規格として定めており、国際的取引・共同開発において重要な役割を果たします。
工業規格への準拠により、製品の信頼性が向上し、調達・生産の効率化、コスト削減にも寄与します。国内では、JIS(日本産業規格)も工業規格の一種です。
マネジメントシステム規格
マネジメントシステム規格とは、企業・組織が効果的かつ効率的に運営・管理を行い、継続的な改善を実現するための仕組みを標準化した国際規格です。製品・サービスそのものの仕様ではなく、企業・組織の運営・業務プロセスおよび管理手法に関する枠組みを定めたもので、業種・業界を問わず活用されています。
マネジメントシステム規格は、「PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)」に基づいた継続的な改善を前提としており、企業・組織の信頼性向上、業務効率化・リスク管理体制の強化などに有効です。マネジメントシステム規格に基づく認証の取得により、対外的な信頼性・競争力を高める効果も期待されます。
ISOマネジメントシステム規格の代表的な種類一覧

ISOには多種多様な種類の規格があり、業種・業態、事業規模、経営方針に応じて、導入する規格を適切に選定する必要があります。以下では、ISO規格の代表的な種類の概要および特徴について解説します。
ISO9001(品質マネジメントシステム)
ISO 9001は、品質マネジメントシステム(QMS)に関する国際規格で、顧客満足度・信頼性の向上を目的としています。ISO9001では、製品およびサービスの品質を一定に保ち、組織全体で品質管理を行うための仕組みやルールが定められており、業種・規模を問わずあらゆる組織で適用可能な規格です。PDCAサイクルを基盤とした評価・改善の仕組みにより、リスクベースでの思考と予防体制の構築も実現します。
ISO14001(環境マネジメントシステム)
ISO 14001は、環境マネジメントシステム(EMS)に関する国際規格です。環境への負荷を最小限に抑えながら、持続可能な事業活動を実現するための枠組みとして定められています。省エネ・廃棄物削減、法令遵守など、環境リスクの管理と管理体制の継続的な改善を重視しており、企業の信頼性向上および社会的責任(CSR)の強化にも寄与します。
環境関連の法令は数が多く、そのすべてを把握するのは困難です。いずれの規格も法令遵守は重要項目であるものの、とくにISO14001では、膨大な法令に対応するための体制構築が重要視されます。ISO 14001認証は業種・規模を問わず導入でき、環境配慮型経営を実践している企業・組織の証明として対外的なアピールにも有効な規格です。
関連記事:ISO9001とISO14001の違いを比較解説|取得企業の特徴とは
ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)
ISO 27001は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格です。企業・組織が保有する情報資産を「機密性」「完全性」「可用性」の3つの観点から、保護・管理するための枠組みを定めています。情報漏洩・サイバー攻撃、内部不正などのリスクを特定・評価し、適切な対策を通じて安全かつ円滑な情報管理体制の構築を目的としています。
関連記事:ISO27001(ISMS)コンサルタントの必要性を解説|最適なコンサルの選定基準とは
ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)
ISO 45001は、労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)に関する国際規格で、働く人々の安全・健康を守る職場環境を構築する枠組みです。労働災害および健康被害のリスクを特定し、予防・改善策を講じて、安全かつ持続可能な労働環境を実現します。PDCAサイクルを活用しながら、法令遵守・従業員の意識向上を図る仕組みです。ISO 45001認証の取得は、社会的責任(CSR)および従業員の企業・組織に対する信頼性向上にも寄与します。
ISO22000(食品安全マネジメントシステム)
ISO 22000は、食品安全マネジメントシステム(FSMS)に関する国際規格です。食品の製造・加工・流通における安全性を確保するための管理体制を定めています。HACCP(危害分析重要管理点)手法を取り入れ、企業・組織全体で食品の安全リスクを管理・改善する仕組みを構築します。食品関連事業者だけでなく、包装・輸送などの関連業種にも適用可能です。
ISO50001(エネルギーマネジメントシステム)
ISO 50001は、エネルギーマネジメントシステム(EnMS)に関する国際規格で、エネルギーの効率的な利用と管理体制の継続的な改善を目的としています。電力・燃料などの使用状況を把握・分析し、無駄の削減・省エネ対策を組織的に進める仕組みを構築する枠組みです。PDCAサイクルを活用しながら、エネルギーコストの削減と環境負荷低減の両立を図ります。ISO 50001認証の取得は、企業・組織の省エネ・環境保護に対する姿勢を対外的に示し、持続可能な経営の実現にも貢献します。
ISO13485(医療機器マネジメントシステム)
ISO 13485は、医療機器の品質マネジメントシステムに関する国際規格です。企業・組織における、安全かつ有効な医療機器の設計・製造・供給を実現するための基準を定めています。ISO 9001を基にしながらも、医療業界特有のリスク・文書管理、サプライチェーン全体で製品の移動を追跡するトレーサビリティ、是正処置などに重点を置いている規格です。製造業者だけでなく、関連するサプライヤー・サービス提供者にも適用可能で、医療機器に関する国内外での信頼性確保、および市場競争力強化に貢献します。
ISO認証を取得する手順

ISO認証を取得する際は、以下の手順で体制構築・審査対応を行います。
- 取り組む体制を決定する
- マネジメントシステムを構築する
- マネジメントシステムを運用する
- 審査機関による登録審査を受ける
- 登録証の発行を受ける
以下では、手順ごとの詳細について解説します。
1.取り組む体制を決定する
ISO認証に対してどのような方針、体制で取り組むのかを決定します。方針では、例えば、現在の業務をそのままISOマネジメントシステムに載せるのか、あるいは改善を含めて取り組むのかということを決定します。また、推進体制をどうするのか、部門横断のプロジェクトチームを結成する、コンサルタントに支援してもらうなどが考えられます。単に“認証登録証をもらう”のではなく、業務との整合性、効率も考えた方がよいでしょう。
2.マネジメントシステムを構築する
ISO認証を取得するには、対象となる規格に沿ったマネジメントシステムの構築から着手します。単なる書類・業務手順の整備ではなく、企業の業務プロセスおよびルールの明文化、品質・環境・情報セキュリティなどの管理目標に向けて、計画的かつ継続的に管理できる体制の構築が目的です。
たとえば、品質目標の設定、リスク評価、業務手順書の整備、責任分担の明確化などが含まれます。自社の実態に即したマネジメントシステムの構築が、認証取得の基盤となります。
3.マネジメントシステムを運用する
構築したマネジメントシステムは、実務で継続的に運用・実践します。規定した手順に準拠して業務を遂行し、記録作成・保管、発覚した課題に対する是正処置・予防処置を講じながら、システムの有効性を検証・改善します。社内教育・定期的な会議を通じて全社員の意識を高め、マネジメントシステムの浸透・定着を促進する施策も必要です。マネジメントシステムの運用実績がなければ、審査機関からの認証は得られません。一般的には3カ月以上の運用期間が推奨されています。
4.審査機関による登録審査を受ける
ISO認証の取得には、第三者である審査機関による登録審査(初回審査)を受ける必要があります。審査は通常二段階に分かれており、第一段階審査では、マネジメントシステムの整備状況および運用ルールが規格に適合しているかを確認します。認証取得にあたり、文書作成が必須ではなくなった影響から、第一段階審査でも文書審査に加えて実地審査が実施される傾向があります。
第一段階審査で問題がなければ、第二段階審査における実地審査(現地審査)で、実際の運用状況および記録類、マネジメントシステムで定めた基準に準拠して業務を遂行しているか確認します。ISO規格の要求事項に対する不適合が指摘された場合は、是正処置の実施が求められ、再審査で是正処置の効果が認められた場合、認証が付与されます。
関連記事:ISO審査の流れを解説|認証取得までの流れや必要な準備とは?
54.登録証の発行を受ける
審査機関による登録審査(初回審査)に合格すると、ISO認証の登録証(認証書)が発行されます。これは、企業・組織におけるマネジメントシステムが国際規格に適合していることを正式に証明する文書です。
登録証には、適用規格・認証範囲・認証番号・有効期限などが記載されており、登録証の発行後は対外的に認証の取得を公表できる状態となります。ただし、認証は永続的ではなく、有効期間は通常3年間です。有効期間中は、最低年1回の維持審査(サーベイランス審査)を受ける必要があり、有効期間後も継続的に認証を維持する場合は、3年ごとに実施される更新審査で要求事項への適合を証明する必要があります。
関連記事:サーベイランス審査(定期審査)とは?ISO認証の仕組みや審査の流れと対応方法を解説
総括
本記事では、企業・組織の活動に関わる主要なISO規格の種類とその特徴を体系的に解説しました。ISO規格の種類は品質・環境・情報セキュリティなど多岐にわたり、導入する規格を選定する際は業種・経営方針に応じた判断が不可欠です。自社に最適な規格を見極め、適切な規格の取得・運用により、信頼性の獲得・国際的な競争力の向上が見込まれます。
この記事の編集者

QFSjapan編集部
ISO審査・認証サービスを提供する「株式会社QFSjapan」が運営。ISOを新たに取得する方や、すでに運用中の方のお悩みや知りたいことを中心にお届けします。ISOの専門家として、信頼できる情報をISO初心者の方でも分かりやすくお伝えできるよう心掛けていきます。